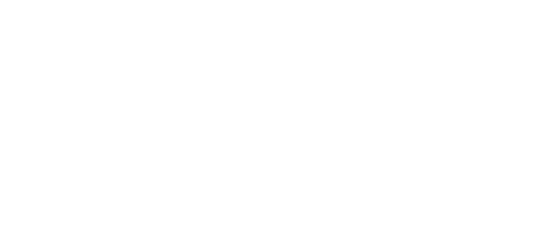前回の続きで社宅家賃の計算方法について見ていきます。
社宅については、税務上徴収すべき家賃(賃借料相当額)が定められていて、次の金額以上を本人から徴収していれば給与として課税されることはありません。
賃借料相当額の計算は従業員と役員で異なります。
1.従業員
① 建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%
② 土地の固定資産税課税標準額 × 0.22%
③ 12円 × 坪数
④ ①~③の合計 × 50%
算式中の率や数字は社宅を維持するための保険料や修繕費等を数値化したものです。この算式ができたのが昭和26年なので、長屋の社員寮のイメージで計算されています。
実際に計算すると5000~10000円ぐらいには納まります。
2.役員
≪梅≫(木造なら40坪、RCなら30坪以下)
① 建物の固定資産税課税標準額 × 0.2%
② 土地の固定資産税課税標準額 × 0.22%
③ 12円 × 坪数
④ ①~③の合計
ほぼ従業員と同じ計算ですが④で50%を掛けない点が違います。
≪竹≫(木造なら40坪、RCなら30坪超)
① 建物の固定資産税課税標準額 × 12%(耐用年数30年超なら10%)
② 土地の固定資産税課税標準額 × 6%
③ ①~②の合計 × 1/12(年額⇒月額)
④ 賃貸物件であれば借り上げ賃料の半分と③の高い方
梅に比べると自社物件であっても3倍以上、借り上げ社宅であればさらに高くなるため、面積は重要な要素になります。
≪松≫(240㎡以上)
① 時価相当額(周辺家賃と同じ水準)
つまり家賃そのままです。
3.注意点
・自社物件なら固定資産税評価額が分かりますが、賃貸物件の場合は通常分かりません。契約時に家主に聞くか、契約書を持参して市役所で確認するかのいずれかの方法を取ります。
・面積については、共有部分の面積もあることから、賃貸契約書、登記、固定資産税でそれぞれ異なることがあります。面積によって社宅家賃が大きく変わりますので慎重に確認しましょう。
4.結局どっち?
従業員にとっては補助額が同じなら社宅の方が手取りが増えるので嬉しいです。
住宅手当の場合、所得税と住民税を合わせて約20%、社会保険料が15%ほどかかるので、手当の1/3が税金で消えてしまいます。
一方、社宅は手間がかかるので、家賃補助が1~2万円であれば住宅手当の方が簡単でいいかも知れません。
逆に本人負担が1万円までと少なく、残りが会社負担であれば、手取りへの影響が大きいので社宅家賃とした方がいいかも知れません。